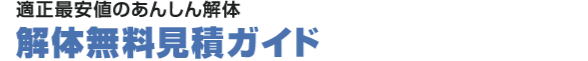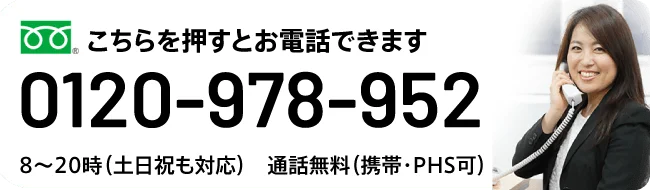抵当権のある建物の取り壊し
抵当権とは?
抵当権とは、いわゆる「担保」と似たような意味を持つ言葉で、住宅ローンの貸し倒れを防ぐために設定される権利のことです。
住宅ローンの貸し主である金融機関などは、万が一、借り主が返済能力を失った場合などに備え、建物を担保に設定することができます。
借り主が住宅ローンを支払わず督促にも応じない場合、貸し主は担保となっている建物を競売にかけて売却することで、貸付金を回収することができます。
このように、貸付金回収のための担保となっている建物のことを「抵当権」のついた建物などと呼びます。
なお、抵当権によって貸付金を回収できる立場の貸し主を「抵当権者」、建物を抵当権に設定されている立場の借り主を「抵当権設定者」と呼びます。
抵当権の設定方法
住宅ローン契約を結んだあと、抵当権者と抵当権設定者とで「抵当権設定契約」を結びます。
その後、建物の所在地を管轄する法務局に必要書類を提出し、抵当権の設定登記申請を行います。
抵当権設定に必要な書類は、以下の通りです。
抵当権設定に必要な書類
- 抵当権設定契約証書
- 設定者の登記済権利証
- 設定者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
- 設定者の委任状(実印を押印したもの)
- 抵当権者の委任状
- 抵当権者の資格証明書(発行後3か月以内のもの)
抵当権のある建物でも取り壊せる

抵当権のついた建物であっても、一定の条件を満たしている場合においては取り壊すことが可能です。
具体的には、抵当権設定者が住宅ローンを完済していることが大前提となり、取り壊す前に抵当権者の同意も必要となります。
ここからは、抵当権つきの建物を取り壊すための条件や注意点を、詳しく確認していきましょう。
借金の完済があるのが前提条件
住宅ローンが完済できていない場合、取り壊しは原則不可能です。
抵当権つきの建物は、住宅ローンが返済できない場合の担保となっています。
つまり、住宅ローンが残っている状態では、担保としての役割もまだ残っている状態となります。抵当権つきの建物を取り壊すならば、住宅ローンを完済していることが大前提となります。
建物滅失に関する同意書を準備する
住宅ローンを完済している抵当権つきの建物は、抵当権者の同意のもと取り壊すことが可能です。
取り壊し後のトラブルを防ぐためには、抵当権者が取り壊しに同意していることを書面で残しておく必要があり、そのためには「同意書」の作成が必須となります。
同意書のフォーマットに指定はなく、取り壊し(建物滅失)に同意している旨と併せて、抵当権者の連絡先や建物の詳細を記載し、押印するのが一般的です。
なお、抵当権者が金融機関などであれば、同意書はスムーズに発行してもらえることが多いです。
同意書作成後に行う手続き
同意書の作成が済んだら、一般的な取り壊しと同様の流れで工事を進めていきましょう。
工事の完了後は法務局にて「滅失登記」を行いますが、先に作成した同意書も添付するのが一般的です。
法務局は「抵当権者から滅失の許可を得ているか?」の確認を行うため、同意書を添付することで同意がある旨をスムーズに証明できます。
ただし、滅失登記における同意書の添付は義務ではありません。
なお、滅失登記が完了すると自動的に抵当権も抹消されるため、抵当権抹消に伴う手続きは必要ありません。
抵当権のついている建物の撤去・滅失登記の実例
実際に、抵当権つきの建物の撤去・滅失登記について悩まれている方の実例をみていきましょう。
質問:
建物を解体する予定ですが、銀行の抵当権が付いています。
1.抵当権付のまま解体して問題がありますか?滅失登記は可能ですか?
2.銀行に抹消について了解をもらう予定ですが、その後解体、滅失登記の流れを教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答:
1.建物を解体し、滅失登記をすれば当然に抵当権は消滅します。建物滅失登記に抵当権者の承諾書は添付は不要です。
しかし、債権者の承諾無く、抵当権を設定した建物を解体した場合、民法137条第2号の「担保の滅失」にあたり、期限の利益を主張することができなくなります。つまり、債権者である銀行が弁済期を待たずして、貴方に貸金の返還を請求することができるようになるので、建物の解体の了解をもらったほうがよいです。恐らくその場合は、他の担保(不動産なり保証人)なりを求められる可能性が高いです。
2.銀行の承諾を得た上で、建物を解体し、滅失登記をするだけです。なお不動産登記法上は抵当権の抹消登記は不要ですが、司法書士によっては、一応したほうがよい、などといわれるかもしれません。
(期限の利益の喪失)
第137条
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
引用:おしえて!goo
これまで本記事で解説してきたように、抵当権つきの建物であっても、取り壊しは可能であることが分かります。
また、滅失登記には承諾書(同意書)の添付が不要と回答されていますが、同時に、抵当権者からの同意を得ずに取り壊しをするリスクについても言及されています。
つまり、同意書の作成に法的な義務はないものの、抵当権設定者にとっての不利益や民事訴訟などのトラブルを防ぐためにも、同意書の作成が推奨されているということです。
抵当権についてのまとめ
住宅ローンを完済した時点で抵当権を抹消しておけば、建物を取り壊す際の抵当権に関する手続きは不要です。
とはいえ、抵当権の抹消手続き自体に手間や費用がかかるため、住宅ローン完済後も抵当権を抹消せずに放置している方が多いです。
そのため、いざ建物の取り壊しを検討しはじめたときに「抵当権がついたまま建物を取り壊せるのか?」という疑問が湧いてきます。
抵当権つきの建物の取り壊しは、住宅ローン完済を前提とし、抵当権者からの同意を得たうえで行うことができます。
取り壊しが完了すると同時に抵当権も抹消されるため、抵当権抹消にかかる手間や費用は不要です。
抵当権つきの建物の解体をお考えの方は、まず抵当権者に相談し、必要な手順を踏んで取り壊しを進めていきましょう。