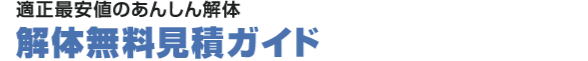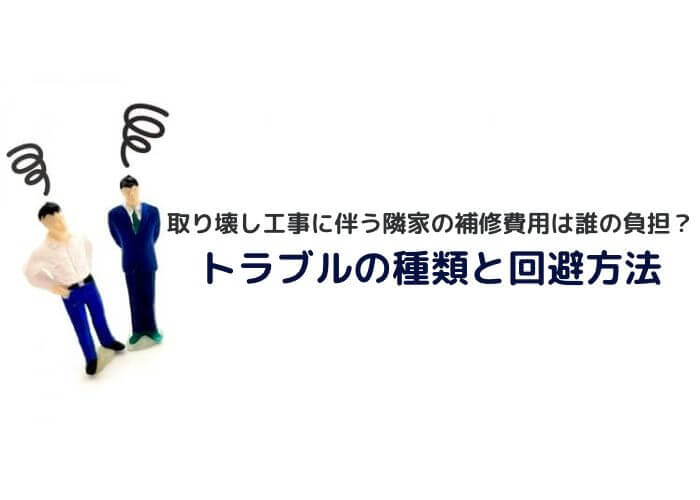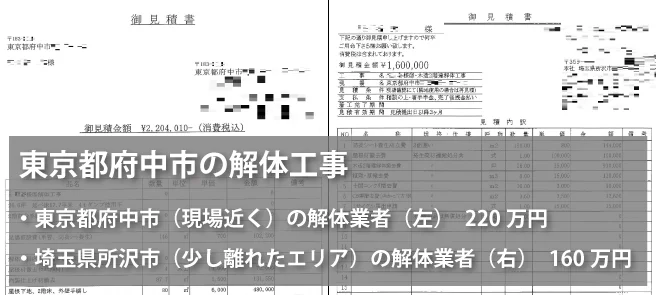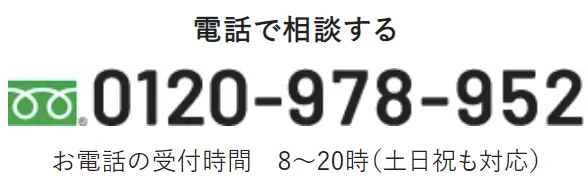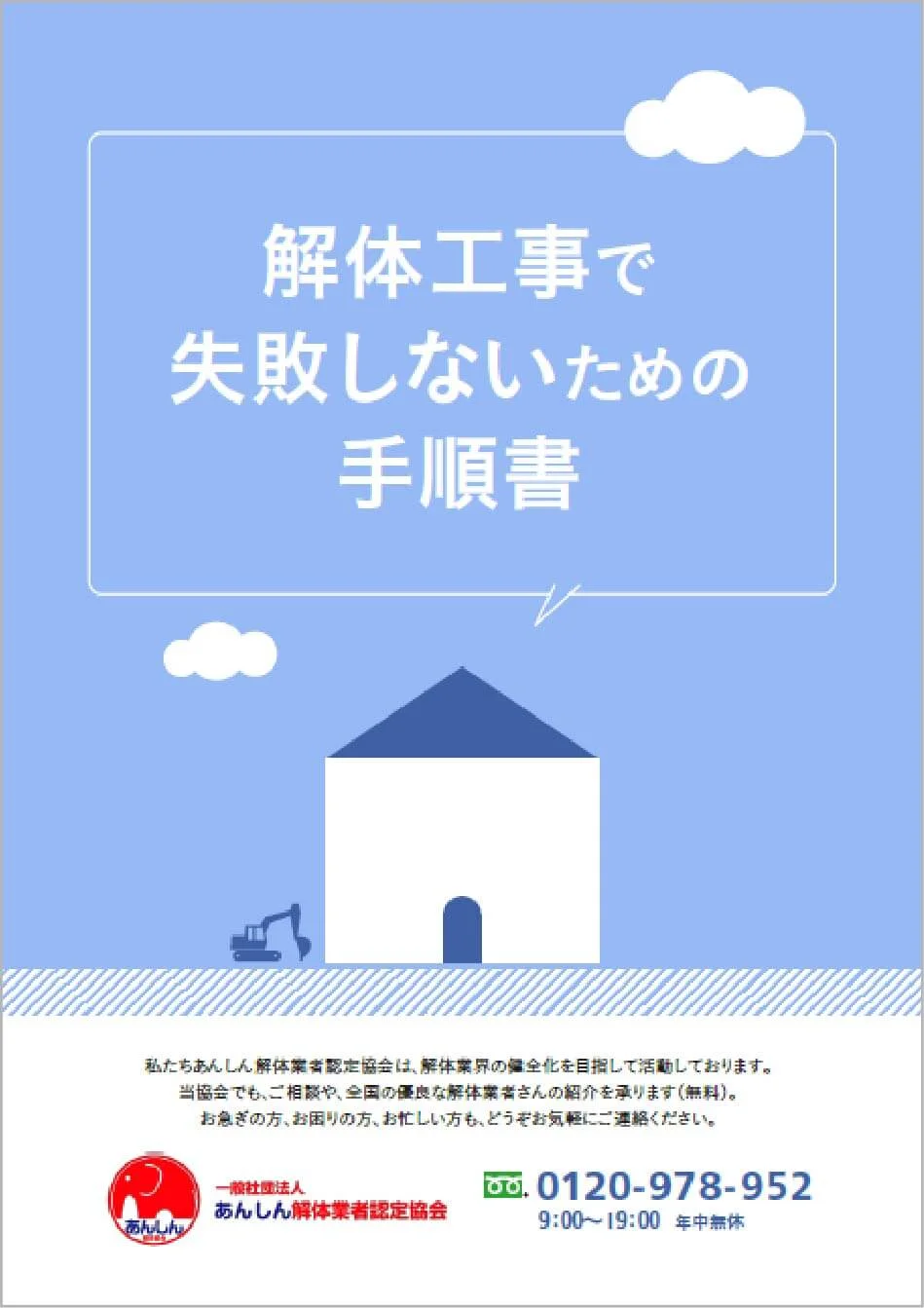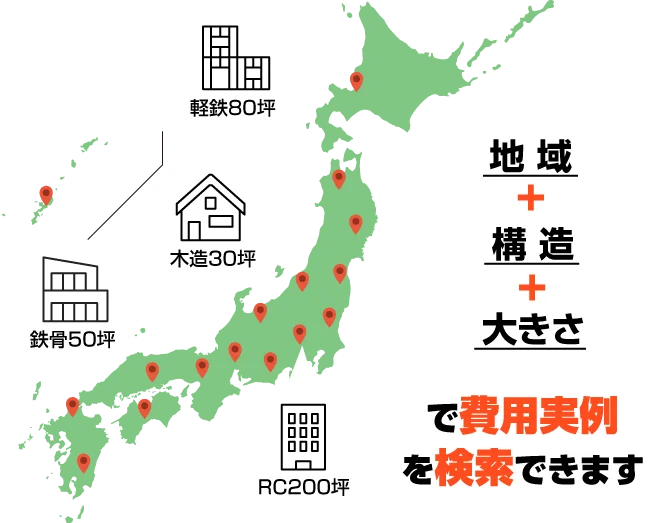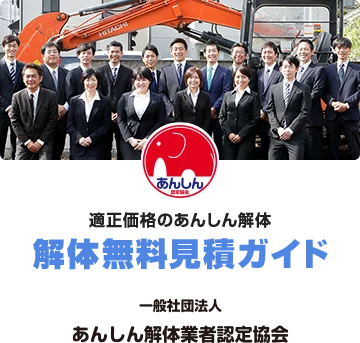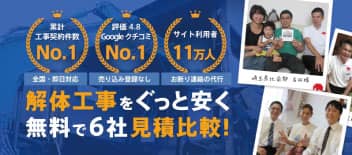建物の解体工事をするにあたって、「隣家との距離がほぼない状態で困っている」と悩まれている方も多いようです。対策が不十分な状態で作業を開始した結果、隣の屋根や壁を損傷してしまい、補修費用を請求されるようなトラブルが起きるケースも少なくありません。
これは、住宅だけでなく、ビルやマンションでもあり得ることです。
では、実際に解体工事でどのような隣家への被害をもたらす可能性があるのでしょうか?また、解体工事によって隣家を損傷してしまった場合、補修工事の費用は誰が負担するべきなのでしょうか?
本記事では、補修工事のトラブルの事例をもとに、対策方法をご紹介します。
建物や壁の崩壊による隣の住宅の破損
解体工事では、「騒音や埃などによって自宅の窓も開けられず、洗濯物が干せない」「境界線を越えての工事に困っている」などのトラブルが考えられますが、隣の住宅に直接的な被害が生じるケースもあります。
解体工事による隣の住宅への破損は、実際には下記のような例があります。
2010年10月、岐阜県で解体途中の壁が崩壊し通行人の高校生が下敷きになってしまった事件が発生。
解体業者は危険性を認識していたのにも関わらず、ワイヤで固定しながら作業するなど適切な工事を行わなかった事が原因です。
また、建物自体が倒壊した事例もあります。
2015年4月に、東京都中野区で解体中の建物が倒れ、隣接した住宅に寄り掛かる事件がありました。このようなことがあると、近隣の方々も不安になりますし、もしも支える建物が無く、さらに人がいるところに倒れていたら大事故に発展していた事でしょう。
寄りかかられた住宅の住民の方々もとても怖い思いをしますし、住宅も傷んでしまいます。
優良な解体業者であれば、事前の現地調査で実際の建物やその立地を見て、事故が起きないように工事を進めるにはどのような対策が必要か詳しく確認します。
また、工事の際に振動が大きくなると事前にわかっている場合には、「工事前・工事後」に近隣住宅の状態を撮影します。そうして写真に残しておくことにより、もしも工事後に近隣住人が自分の住宅の外壁等にできた傷を指摘してきた際、その傷が果たして解体工事によるものなのかどうか、責任の所在を明らかにできます。
解体工事の際に出てしまう破片に関しても、近隣に飛散しないようしっかりとした養生シートで囲い、対策をとります。養生シートに穴が空いていたり破れていたりすれば破片の飛散を完全には防げませんし、誰かの足が引っかかって事故に繋がるケースも。
事故が起きない工事をしてくれる解体業者を見極めるには、下記のポイントを押さえておく必要があります。
- 現地調査を入念に行ない、隣の建物までの距離がどれくらいなのか、重機は安全に使用できるのか等を含め、しっかりと確認をとる解体業者であるか
- 手入れされた養生シートを使用する解体業者であるか
住宅の解体をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
重機や車両の横転、衝突による隣の住宅の破損
大きく重量のあるクレーン車やブルドーザーは工事現場では欠かせない重機ですが、これらがもし倒れてきたら、ひとたまりもないことでしょう。
2015年5月には、作業員が下敷きとなる重機横転事故が起きました。
作業現場は数々の廃材が重なり、地面に廃材の山が転々と出来てしまってたそうです。
そんな足場の悪い所を、かなり重量のある機材を運んでいた重機が通ろうとして足元をすくわれた事と、現場で正確な指揮が取れていなかった事が原因と言われています。
さらに、工事中のトラックが通行人や自転車、一般車両と衝突する事故もあります。
工事の際一般道に重機やトラックが止めてあり、事故が起こらないように警備員が一般車両や通行人の誘導をしているのを皆さんもよく目にすると思います。
しかし、監視役が持ち場を離れてしまったり、業者によってはコスト削減のため監視役を雇わなかったりしたために事故が起こってしまった例があります。2015年10月に、引退間近の盲導犬とパートナーの男性がダンプカーに轢かれた事故も起きました。
ダンプカーが方向転換のため資材置き場にバックで入ろうとした際、運転手から死角になっていて被害者の姿を確認できなかった事が原因のようです。さらに、運転手が「バックします」とバックを知らせる警報音声のスイッチを切ってしまっていた事も判明しました。
運転手が後方を確認したつもりでも、トラックやダンプカーといった車体の大きい車両は死角が多いため、見える範囲が限られます。
足場が悪く、見通しも悪い工事現場では、的確な指示や計画的な動きがとても大切です。運転手が気をつけているつもりでも大型車の視界には限界があります。依頼主は、現場の監視役や交通誘導員を雇い、事故が起きないための十分な対策をとってくれるかどうか、業者に確認するようにしましょう。
実際に起きた隣の住宅とのトラブル事例
それでは、実際に起きた隣の住宅とのトラブル事例を見ていきましょう。
よく起こる主なトラブル事例は、下記の通りです。
- 隣の住宅との距離がなく、解体工事中に隣の住宅の外壁がむき出しになってしまった
- 地盤が緩んだことにより建物が傾いた
- 土砂崩れが起きた
- 駐車場の地面コンクリートにヒビが入ってしまった
- 住居の内壁に亀裂が入った
- 天井が垂れ下がってしまった
隣の住宅の損傷による悩みを抱いた方の声
こちらは実際に解体工事に伴う隣の住宅の損傷による悩みを抱いた人の声です。
土地の所有者ですが、現在、三軒長屋を含むその他の家屋を裁判所の指示による撤去の最中です。その三軒長屋のうち真ん中の家は旧家屋所有者より現住者が購入しています。現住者より両隣を壊されると自分の住宅まで崩れてしまいそうだと苦情がきました。住宅の補強費用の負担を求められた場合負担をしなければいけないでしょうか?
今回のお悩みは、まだ「崩れてしまいそう」の段階ですが、実際に隣の住人に補修工事の費用を求められた場合、解体工事の施主側が隣家の補修費用を払うべきなのでしょうか。
ついでにもう一つ、施主と隣人の間に起きたトラブルの事例を見ていきましょう。
隣人Bさんから「玄関にひび割れが起きている」というクレーム
業者が、Aさんという方から依頼を受けて解体工事を行ったときのことです。
工事施工後に、施主のAさんの隣人であるBさんから業者に連絡が入りました。
なんと、「解体工事の影響で玄関にひび割れが起きてしまった」というのです。
Bさんはひび割れの修復費用を請求したいと申し入れました。
工事業者は近隣へ影響を及ぼさないよう丁寧に施工していたはずでしたが、慌ててBさんの自宅へ赴き、現場の確認をさせてもらいました。
しかし、確認してみるとそのひび割れは明らかに古いもので、解体工事により最近にできてしまったものではなかったのです。
つきつめると、以前からの不仲が原因だった
業者が「ひび割れは過去にできたものではないか」と指摘すると、Bさんはそれを認めました。なんでも、「過去にAさんから受けた身勝手な行動を未だに許すことができず、何らかの形で償ってもらいたかった」と言うのです。
Bさんは業者でなく、Aさんに修復費用を請求したかったのだと言いました。
BさんとAさんには、過去に次のようなトラブルがありました。
・Aさんが、Bさん宅共有のブロック塀に「植木をかけたいから」と勝手に鉄の柵を入れた
・Aさんがブロック塀に相談なく釘を打ち、釘がBさん宅まで突き抜けてしまっていた
・Aさんが貫いた釘に引っかかり、Bさんが怪我をしてしまった
業者では解決できないトラブル
この場合、AさんとBさんの間に起きたトラブルは取り壊し工事とは無関係なため、業者が責任を負うことはできません。
業者はBさんから、「Aさんに玄関のひび割れの修復費用を請求したい」との相談を受けましたが、玄関のひび割れの直接的な原因がAさんにあると証明できなければ、Aさんが費用を支払うこともないでしょう。
しかし何かしらの報復をAさんが受けない限り、納得がいかないとBさんは言います。
このような場合、話し合いでの和解以外に道はありません。
業者にできることは中立の立場に立ち、両者の仲を取り持つことくらいです。また、その義務が業者にあるわけでもありません。
つまり、トラブルが起こってしまってからでは明確な解決策となるものはなく、いずれにしても未然に防ぐ必要があるのです。
このようなトラブル事例とその原因を知っておくことで未然に防ぐことが可能です。次に、隣の住宅との補修工事の費用負担や保険などをご説明していきます。
隣の住宅の補修工事に関する法律や損害賠償保険について
隣の住宅が解体工事で損傷した場合、補修工事の費用負担は誰がどのように責任を負うかは2つのケースに分けられます。
1.工事業者の不注意や不手際で隣家を損傷したケース
解体工事の作業中に、隣家の建物が損傷してしまった場合は、民法709条に基づき業者が損害賠償金を支払うことになります。
第七百九条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
この場合、工事業者が損害賠償保険に加入しているかを確認する必要があります。
損害賠償保険に未加入の業者は未だにいるそうなので、業者を選ぶ際は必ず確認してください。
損害賠償保険の加入の有無だけではなく、「加入している保険の限度額はいくらか」「事故の適用範囲はどこまでか」といったことまでの確認もしておくとよいと思います。
可能であれば、保険証券のコピーを見せてもらって内容を把握しておくと安心です。
2.工事を依頼した施主側の責任になるケース
基本的には民法第716条により、依頼者である施主に損害賠償責任はありません。
しかし、民法第716条のただし書きにもあるように、施主側が注文または指図した場合は責任を負うこともあります。
第七百十六条(注文者の責任)
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
例えば、施主の指示に問題があった場合や、逆に施主が何も指示をしなかったがために事故に繋がった場合も施主側の責任になります。
つまり、施主が取り壊し工事中に隣の住宅への被害を発見した、あるいは、被害がさらに大きくなることが想定できたにも関わらず、業者に伝えることなく工事を止めなかった場合は、「過失」とみなされる場合があるのです。
取り壊し工事での損害賠償保険の種類
取り壊し工事での賠償保険にも様々な種類があり、代表的なものとして下記の保険があります。
-
会社単位の保険
会社単位で加入する保険です。年間の売上金額によって保険額が決定し、その年の全ての工事が保険対象になります。
-
工事単位の保険
工事現場ごとに加入する保険で、工事の請負金額により保険料が決定し加入した工事にのみ適用される保険です。通常よりリスクの高い工事現場だけに加入されることが多いです。
-
車両単位の保険
重機やトラックなど、車両単位で加入する年間の保険で、それらの機械が関係する工事だけに適用される保険です。
隣の住宅を損傷し、補修する必要がでてくるような直接的なトラブル以外にも、従業員が負傷する事故や、解体工事中に外壁が倒壊し、通行人や車などに接触してしまうトラブルも考えられます。
万が一作業中に事故が発生した場合、賠償保険に加入していない業者は負担額を支払うことができず、費用をお客様が負担しなければならない可能性もあります。
そのため解体業者を選ぶ際は、損害賠償保険に加入の有無を必ず確認しましょう。
解体無料見積ガイドでご紹介する認定解体業者は、万が一の事故を保証できる「賠償保険」に加入しています。
隣家の住民と補修工事で揉めないための対策
工事業者の過失により隣の住宅を損傷した場合、補修工事の費用について、解体工事を依頼した施主側には、法律的に損害賠償責任がないことが原則だということがお分かり頂けたと思いますが、前提として工事業者の協力が必要不可欠です。
では、隣家と補修工事などによるトラブルに陥らないためには、解体工事前にどんな対策がとれるでしょうか。
工事協定書を作成する
建物の前のスペースが狭い場所や条件が悪い場所での取り壊し工事の際は、工事協定書を作成することがあります。
工事協定書は、工事期間、作業時間、車両侵入方法、警備員の配置などを書面にしたもので、発注者、施工者、隣家の住民の間で約束事を記録するものです。これは、商業施設などの大規模工事で作成するケースが多いです。
ただし、工事協定書を作ることは、解体業者の義務ではないとされています。解体業者側が作ると、業者側に有利な協定書を結ぼうとする場合もあるので、法令の遵守、危険防止、完成後の補償など、なるべく細かく具体的に規定しておいたほうがよいでしょう。
また、業者側が「誠意をもって対応するものとする」のような曖昧な書き方の協定書は危険ですので注意してください。
解体無料見積ガイドでは、工事協定書の作成をご希望の場合、テンプレートのご提供や作成にあたってのご相談も承ります。
工事前に住居調査をする
工事開始前の住居調査も重要です。
解体工事で隣家にリスクがありそうな箇所は、家屋のひび割れや傾きの有無、外壁や基礎、家屋内部の壁や天井なども工事前に写真を撮るなどして記録に残しておきましょう。
解体工事の途中にその工事前の状況から変化が生じていることが分かった時点で、場合によってはすぐに補修工事にとりかかる必要がでてくるでしょう。
そして、それ以上の被害が出ないための対策を業者に求めることも施主として必要なことです。