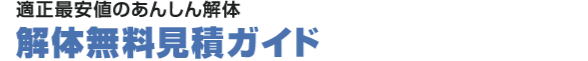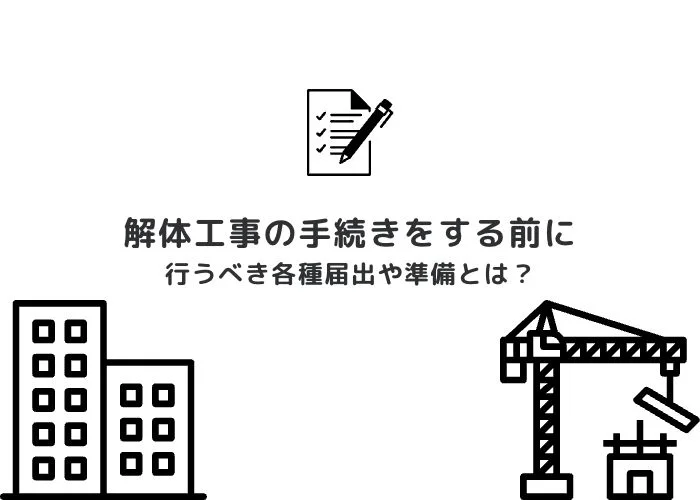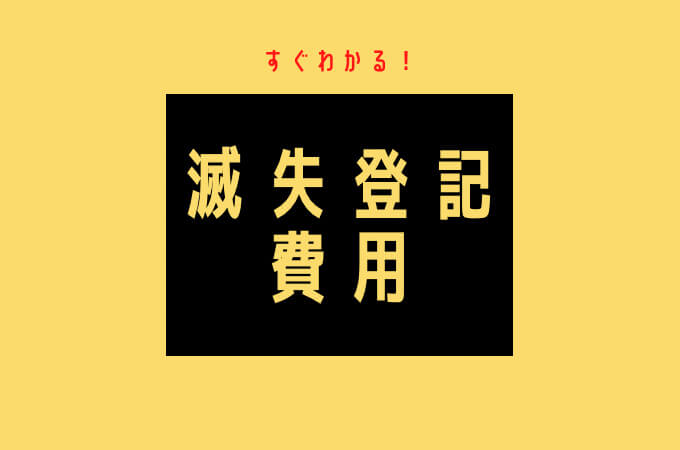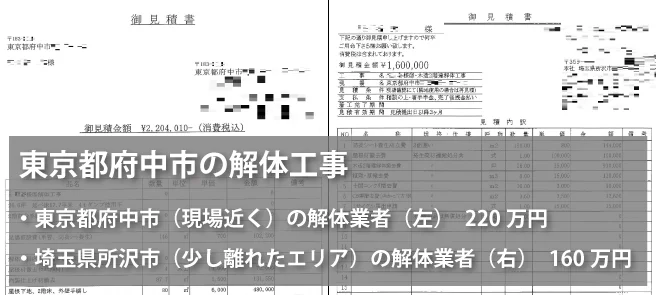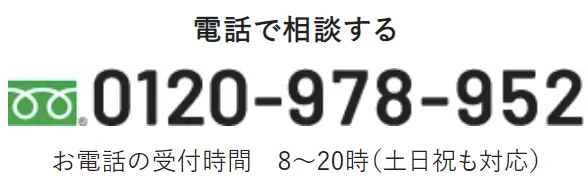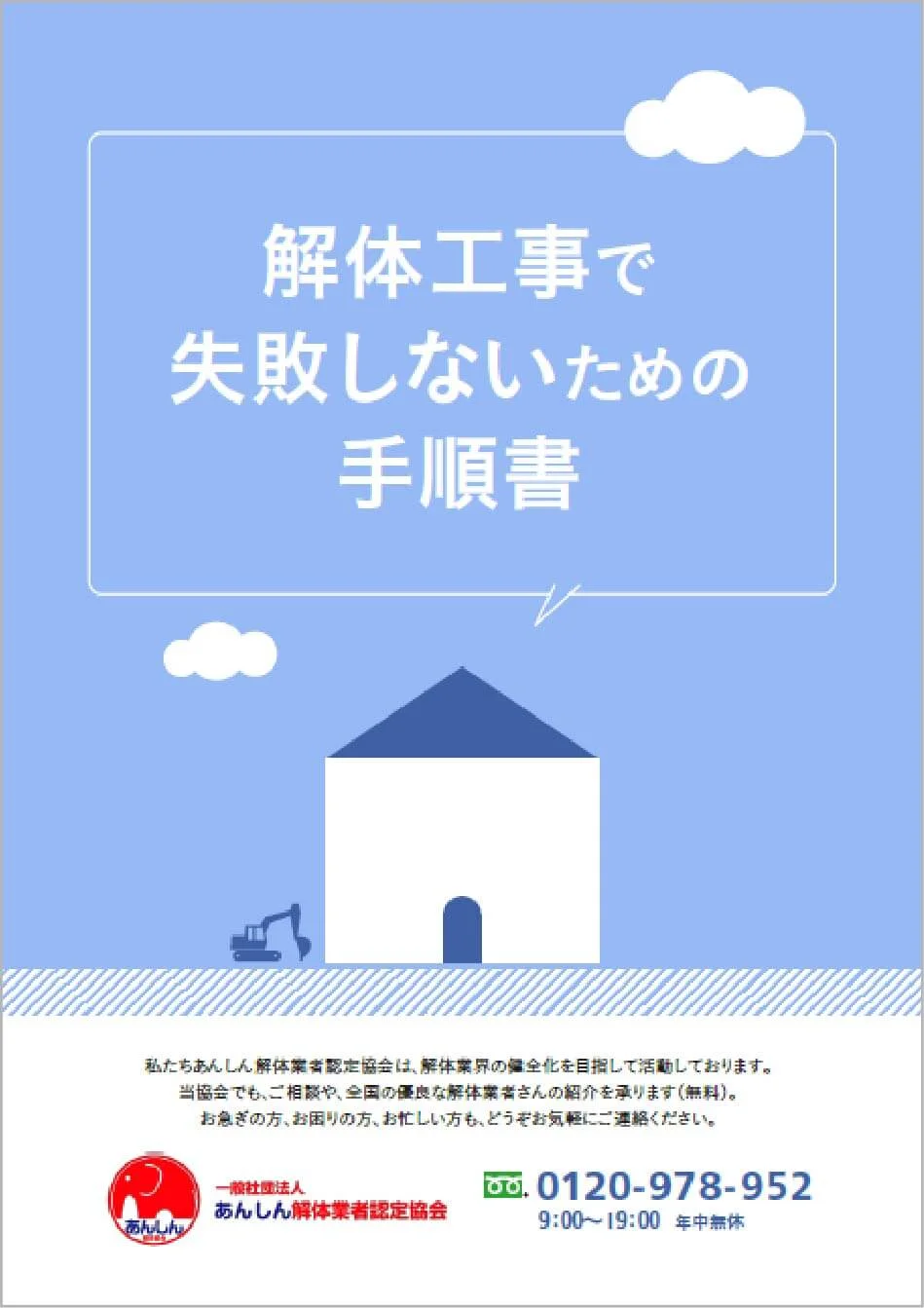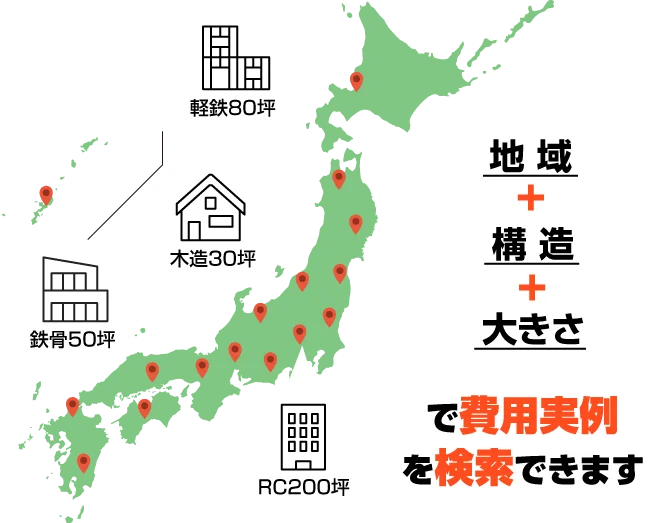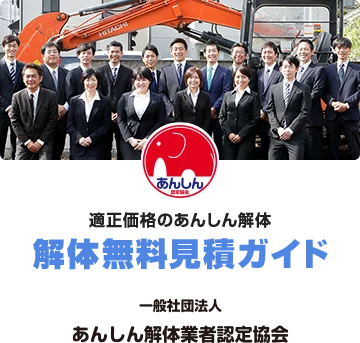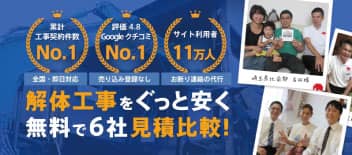解体工事って、費用が高くつくので大変ですよね。
しかし、やり方次第で、費用をグッと抑えることが可能です。
例えば、解体工事の手続きは、解体業者にすべてお願いするより、自分でやる方が費用を抑えられます。
そこで、この記事では、解体工事の手続きをする前に行うべき各種届出や準備について詳しく解説していきます。
解体工事に必要な届け出と手続きを自分で行いたい方は、解体業者へ交渉しつつ、ぜひ参考にしてください。
解体無料見積ガイドでは、相見積もりをとった解体業者への価格交渉など、業界トップの実績と中立的な立場を最大限活用して、お客様のご希望にお応えできますようサポートいたします。
解体工事を行う前に必要な各種届出と手続き
解体工事の前には、「ライフラインの停止手続き(電気・ガスなど)」「行政への届け出(建設リサイクル法など)」が必要になります。
建設リサイクル法の申請
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)は、建築現場や解体現場から排出される廃棄物を正しく処理し、再生資源としてリサイクルするために定められた法律です。
届出の手続きには、届出書・分別解体計画表・付近見取り図・建築物の写真・工程表などが必要になります。解体無料見積ガイドからご紹介している優良業者は、これらの書類を着工の7日前までに都道府県知事へ提出しております。
なお、届出が必要になるのは、延床面積の合計が80m²以上の「特定建設資材」を含む建物を取り壊す工事です。その他、コンクリートやブロック等による工作物でも請負代金が500万円以上のものは、建設リサイクル法の対象になります。
建設リサイクル法の届出は、解体業者が代行するのが一般的です。ただし、建設リサイクル法の届出の義務は施主にあるため、代行にあたっては委任状が必要になります。
道路使用許可の申請
解体工事を行う敷地内に駐車スペースを確保できる場合は必要ありませんが、やむを得ず公道に重機などを駐車する場合は道路使用許可が必要です。道路交通法に基づき、申請は義務付けられています。
第七十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。一.道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
道路使用許可は、一般的には解体業者が有償で申請します。見積書に「道路許可申請費用」という項目があるかどうか、実際に道路使用許可をきちんと提出しているか、解体業者へ確認しましょう。
道路使用許可の申請は、施主でも可能です。自分で行った場合、解体業者に委託するよりも金額は抑えられます。申請自体はそれほど難しくなく、駐車方法を記した図面と道路使用許可申請書を所轄の警察署長へ提出すれば完了します。
ライフラインの停止
工事の前に、電気、ガス、インターネットなどのライフラインの停止やケーブルなどの撤去の手続きが必要です。工事は建物だけではなく、設備の部分も撤去する必要があるためです。ライフライン停止の手続きは、工事開始の1週間前までには終えるようにしましょう。水道は工事中に使用するため停止しない場合があります。
浄化槽の汲み取り(中身の処理)依頼
浄化槽を使用している場合、解体業者に撤去して貰う必要があります。
そのままでは解体業者も撤去することは出来ないので、浄化槽の汲み取り作業をあらかじめ業者に依頼して、きれいな状態にしておくことが必要です。各市区町村によって、浄化槽の扱いは変わってきますので、問い合わせてください。
汲み取り後の浄化槽であれば、解体業者が撤去することができるのでお願いしましょう。金額も大きさによって変動しますが、5~7人槽であれば、3万円~5万円程度の追加料金が相場です。しかし、この項目がなかったり、極端に金額が低い場合は、撤去ではなくその場に埋めてしまう砂埋め方式を採用する場合があります。
浄化槽の砂埋めは、廃棄物処理法違反とされ、処罰される可能性が高いため、撤去してもらうようにしてください。
解体工事業者から出されたお見積もりも確認してみましょう。
アスベスト(石綿)事前調査結果の報告完了を施工者に確認
施工者に対し、アスベスト調査の結果報告が適切に行われているか確認しましょう。
施工者には、事前調査の結果を発注者に書面で説明する義務があります。また、次の条件に該当する場合、施工者には事前調査の結果を都道府県と労働基準監督署に報告する義務も発生します。
- 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80m²以上)
- 建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
- 工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
報告には原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」を利用します。このシステムは24時間オンラインで対応しており、1回の操作で都道府県と労働基準監督署の両方に報告できます。書面での報告も可能ですが、その場合は都道府県および労働基準監督署にそれぞれ書類を提出する必要があります。
「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出
アスベストを含む吹付け材や保温材などが使用されている建築物を解体する際には、大気汚染防止法に基づいて「特定粉じん排出等作業実施届出書」を提出する必要があります。この届出書は、着工する14日前までに解体工事を行う地域を所管する自治体に提出しなければなりません。
「石綿飛散防止方法等計画届出書」の提出
次の規模要件のいずれかに該当する場合には、「特定粉じん排出等作業実施届出書」に併せて、環境確保条例に基づく「石綿飛散防止方法等計画届出書」を提出する必要があります。
- 使用されている石綿含有吹付け材の面積が15m²以上
- 建築物の延べ面積(建築物以外の工作物の場合には築造面積)が500m²以上
この届出書は、着工する14日前までに解体工事を行う地域を所管する自治体に提出しなければなりません。
参考 《大気汚染防止法・環境確保条例》特定粉じん排出等作業(アスベスト)に係る届出等 環境局
近隣への挨拶まわり
解体工事は建物の所有者の事情で行うものですが、騒音・振動・粉塵飛散など、近隣に住む方々にも多大な影響があります。きちんと理解と協力を得ていなければ、トラブルのもとになってしまいます。そのため、近隣への挨拶まわりは必ず行うことをおすすめします。
具体的な作業内容や日時をお伝えし、解体工事に対する不安感をなくしてもらうことが何よりも重要です。
近隣挨拶については、こちらの記事で詳しく解説しています。
井戸の処理を検討
敷地内に井戸がある場合は、家屋の解体にあわせて井戸を解体・撤去するかの検討も必要です。井戸は撤去工事の前にお祓いをするのが一般化しているので、解体・撤去を決めた際は事前に近所の神社に依頼しましょう。
当サイトには、井戸の解体・撤去についてまとめた記事があります。詳しくはこちらを参考にしてください。
また、井戸を廃止・変更するにあたって、行政への届け出が必要な場合があります。届け出の内容や必要な書類は、各自治体の地下水に関連する条例や、井戸の規模、工業用か家庭用かによって異なります。お住まいの地域の自治体の窓口やホームページで確認してください。
解体工事後に必要な各種届出と手続き
家屋の解体が完了した後にも、必要な手続きが2つあります。
建物滅失登記の申請
法務局に登記されている建物を取り壊した場合、存在が消滅したことを申請する必要があります。この手続きを行わない場合、解体後も登記上は建物が存在することになってしまいます。そのため、建物を解体してから1ヶ月以内に建物滅失登記を行う必要があると、不動産登記法第57条に定められています。
解体無料見積ガイドでは、工事完了後にご自身で手続きを行うための建物滅失登記マニュアルをご契約いただいた方に無料でお送りしています。
工事中に使用した水道の停止
水道の停止手続きは、解体工事の完了後に行います。電話などで手続きを行うことが一般的なので、書類の提出は必要ありません。
解体工事における水道管の取り扱いは、こちらの記事で詳しく解説しています。